



2025年8月4日
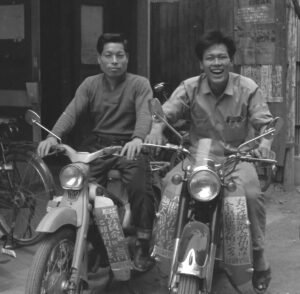 1950年代後半からの高度成長期の個人住宅需要により、技能労働者不足と待遇改善の要求が高まる中で、建設業界は地域の施主への理解を求める運動が中心でした。
1950年代後半からの高度成長期の個人住宅需要により、技能労働者不足と待遇改善の要求が高まる中で、建設業界は地域の施主への理解を求める運動が中心でした。
建設労働者の賃金・労働条件について協定を結ぶ「協定賃金」の歴史は古く、江戸時代にまでさかのぼるといわれています。「太子講」とよばれる職人集団がそれぞれ地域単価の経済情勢の変化にあわせて職人の最低生活を守ると同時に、同業者間の秩序を維持するために「太子講」の組織で協定賃金を決めました。これは第2次大戦後まで続きました。
京建労・全建総連の協定賃金運動を含む賃金運動は、1961年には政府の施策や業界にも影響をもたらすまでの規模に発展。1963年10月23日には京建労単独では初めてとなる、円山公園音楽堂での集会を開き、組合員・家族2000人を集めて、「協賃二千円、建築資材・物価値上げ反対、健保改善」の要求を掲げました。
1970年代に入り、大手住宅資本、プレハブ会社間の低単価競争のしわよせで私たちの賃金や単価に直接転嫁してきていること、そして資本力に物をいわせた大量宣伝によって、在来工法を軸とした町場の住宅市場に進出し、戸建住宅の単価にも大きな影響をおよばしはじめてきているという状況がありました。
全建総連は1976年に、はじめてプレハブ会社、大手建売不動産会社に対する行動を提起しました。
このような運動から、現在も続く大手企業交渉で仲間の声から現場実態を大手建設資本に「要請」として訴える「大手企業交渉」につながっています。1983年にはじまった全建総連関西地協の「大手企業交渉」では、ゼネコン5社、住販企業3社、および国交省近畿地方整備局との交渉を行っています。
 私たちは、労働者・一人親方・事業主を組織している労働組合だからこそ、それぞれの立場で「働き方」について考えることが基本原則。賃金運動を労働者と事業主・親方の対立ととらえるのではなく、町場・野丁場・新丁場において、下請・零細事業主の多数を組織する組合として、労働者・事業主・一人親方が一体となって、対大手資本との「経済闘争」として賃金運動にとりくむ必要があります。
私たちは、労働者・一人親方・事業主を組織している労働組合だからこそ、それぞれの立場で「働き方」について考えることが基本原則。賃金運動を労働者と事業主・親方の対立ととらえるのではなく、町場・野丁場・新丁場において、下請・零細事業主の多数を組織する組合として、労働者・事業主・一人親方が一体となって、対大手資本との「経済闘争」として賃金運動にとりくむ必要があります。
1998年からは協定賃金の設定をやめて、「日額引き上げ要求額」の打ち出しに変更しました。
著しい人材不足に直面する現在、「第三次担い手3法」成立などで、労働組合・国・業界団体がそろって建設労働者の適正な工期・賃金・労働条件の改善を目標に掲げるといったかつてなかった情勢のもとで、建設キャリアアップシステム(CCUS)を力に町場も含めた全丁場の待遇改善にとりくんでいます。
先人たちが声を上げ続けてきた我々建設労働組合の「現場の声」に基づく要求に、大きな意義と任務があるといえるのです。
【建築ニュース1272号(2025年8月15日・9月1日付)】